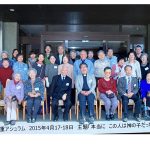2025/02/21
足の裏で読む聖書 -詩篇を味わう-
第1篇「いかに幸いなことか」
詩篇全体の最初を飾る、この第1篇は、「いかに幸いなことか」(1)という印象的な言葉をもって始まる。イエスが、その最初の説教を「幸いなるかな、心の貧しき者は」という祝福の言葉をもってはじめたように、詩篇最初の第一篇もまた、この「幸い」という祝福の言葉によって始まるのだ。詩篇はイスラエル民族、共同体の祈りであり、また詩であった。それは祭儀の中で歌われ、礼拝の中で朗誦されてきた。私たちキリスト教会もまた、「交読詩篇」として、あるいは賛美歌の詩としてそれを用いている。しかしそれは単に典礼として、また儀式の言葉として読まれるだけのものではない。昔から多くの人々が、詩篇の一篇一篇に慰めを得、信仰を強められてきたのだ。「かくなればこそ詩篇はあらゆる聖徒の座右の書となり、いかなる境遇にあろうとも、各人が己の境遇に最適の詩、最適の聖句を見出し、あたかも彼のために特別誂えたるごとく、自分でもこれにまさるものを作ることも望むことも不可能なのを知る」(ルター「ドイツ語訳詩篇第2版序文」より)まさに、詩篇は公同の祈りであると共に、私たち一人ひとりの祈りなのである。それゆえに、この「いかに幸いなことか」という言葉も、これを読む者すべてに与えられた祝福の始まりとなるのである。
さて詩篇には150もの数の詩が集められている。その詩を類型すると、おおまかに「讃美」「嘆き」「感謝」「祝福と呪い」「知恵と教訓」の詩と分けられるそうだ。(「ATD旧約聖書註解書」より)中でも、最も多いのは「嘆き」の詩であり、それは詩篇150篇の約3分の1を占めるという。「主よ私を苦しめるものはどこまで増えるのでしょうか」(3篇)「神よ、私を救ってください。大水が喉元に達しました。私は深い沼にはまり込み 足がかりもありません」(69篇)私たちは、こんな嘆きの言葉を簡単に詩篇の中から見つけ出すことができる。「幸いなことか」という祝福の言葉で始まった詩篇全体の、その内実は、嘆きと悲しみに満ちた人々の神への叫びに他ならない。それはまさに今を生きる私たちの真実の姿を浮かび上がらせる。そしてそれゆえに、読む者一人ひとりの心に詩篇の言葉は深く響いてくるのだ。
詩篇1篇には、この祝福の言葉の後、その幸いな者を「神に逆らう者の計らいに従って歩まず 罪ある者の道にとどまらず 傲慢な者と共に座らず 主の教えを愛し その教えを昼も夜も口ずさむ人」(1-2)と詠う。その人こそ、幸いなのだと詩人は言うのだ。「歩み」、「とどまり」、「座り込む」姿。それはまさに悪の道に入り込み、もう身動きできなくなってしまった神に逆らう者の姿である。流れの滞った澱んだ水ではなく、昼も夜もその教えを口ずさみ、流れ続ける清流の水を汲み上げ成長し、花を咲かせ、実を実らせる「流れのほとりに植えられた木」(3)こそ、幸いなる者の姿なのだ。どんな時であろうとも、どんな境遇の中にあろうとも、とどまらず、座り込まず、日々新たに、主の教えを愛し、それを実践していくこと。これこそが「神に従う人の道」(6)なのである。
祝福をもって始まった私たちの人生も、その中身は、嘆きに満ちているだろう。自分の置かれている現実を目の前にし、途方にくれ、人生の悲しみと苦しみに疲れきって座り込んでしまいそうになる。しかし、そこにとどまり、座り込んではならないのだ。詩篇最後の150篇は、「息あるものはこぞって 主を讃美せよ。ハレルヤ。」という讃美の言葉をもって終わる。たとえどんなに辛く厳しくとも、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ。それこそが、「幸いなことか」と祝福に始まり、「ハレルヤ」と讃美に終わる、神に従うものの姿なのだ。私たちもまた、この幸いな者、神に従う者となろうではないか。
榎本恵牧師のコラム
-
足の裏で読む聖書
(2025/02/21) -
貧しい人と虐げる者とが出会う。主はどちらの目にも光を与えておられる。
(2023/07/31) -
水が顔を映すように、心は人を映す。
(2023/06/21)